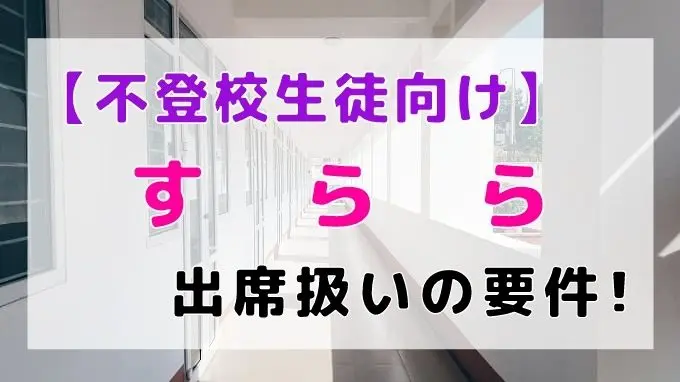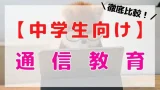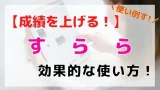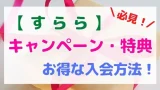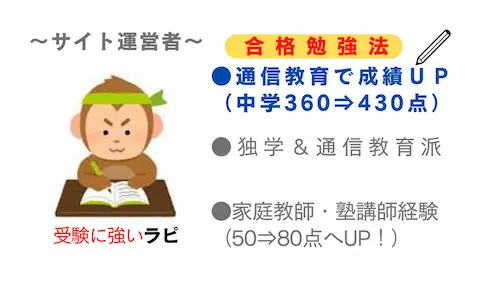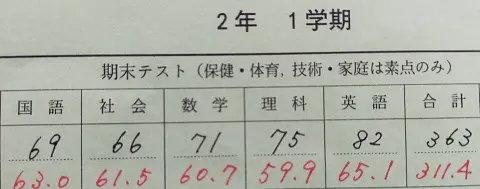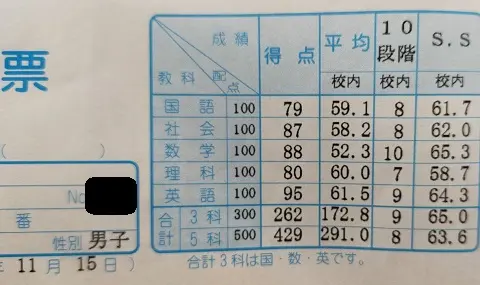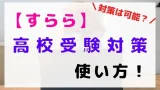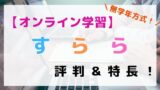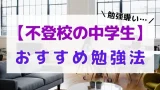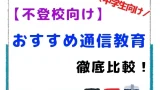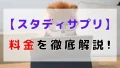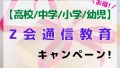~本記事のテーマ~
- すららなら、不登校でも出席扱いにできるって本当?
- 不登校の子供が、すららを使って「出席扱い」にするにはどうしたらいいの?

すららを使って、不登校の子供でも出席扱いにできるって聞くけど、本当かしら?
どうやって出席扱いにするの?
そんな疑問にお答えします!
本記事は、オンライン学習教材「すらら」で、不登校のお子さんを「出席扱い」にする方法を紹介します。
この記事をお読みいただくことで、
- 文部科学省が定める不登校生の出席扱いの要件
- すららを使った不登校の小学生・中学生を出席扱いにする方法
が分かります。
すららを使った出席扱い&すらら受講のメリットをあわせて徹底解説していきますので、不登校のお子さんでお悩みの方は、ぜひご参考にください。
(※本記事は、2022年5月12日現在の情報で作成しています。)
~すららへのお得な入会方法まとめ~
- キャンペーン
- クーポンコード
⇒株主優待のみ! - 入会金無料orユニットクリアキャンペーン
⇒月によってどちらか実施!
※2024年3月は「入会金0円&ユニットクリア200」キャンペーン実施中! - キャンペーンコードは株主優待にて
- クーポンコード
- お得な入会方法
- 4ヶ月継続コース割引
⇒長期継続割引! - 兄弟割引
⇒2人目入会金無料!
≫すらら兄弟利用の詳細はこちら! - 紹介制度
⇒紹介された方は入会金無料!
- 4ヶ月継続コース割引
すららで不登校の子供を出席扱いにできるの?

すららでは、公式HP(≫すらら)にて、不登校でも出席扱いとされる要件を満たすことができる教材とうたっています。
すららの教材は、「無学年式」を用いたオンライン学習教材で、
- さかのぼり学習に最適
⇒学校に行けてなくても授業に追いつける - アニメキャラクターが先生で、楽しく分かりやすく勉強できる
- すららを用いた自宅学習で、出席扱いも可能
という特長があります。
しっかりお子さんの学力を養いながら、不登校でも出席扱いとすることが可能な学習教材です。
とくに中学生のお子さんは高校受験も控えますので、すららで「出席扱い」にしつつ、入試対策の基礎力をつけていけるのは大きなメリットです。
文部科学省の不登校で出席扱いにする要件!

まず、不登校のお子さんでも出席扱いにするための要件から見ていきましょう。
文部科学省では、小学生から中学生を対象として、平成17年に「IT等を活用した自宅学習で出席扱いにできる」という方針を固めています。
不登校児童生徒のうち、学校外における相談・指導を受け、社会的な自立に向けて懸命に努力を続ける子供向けに、学校として評価し支援する目的で、「出席扱い」の制度を作りました。
ただし、不登校生徒を出席扱いにするためには、文科省が定める「不登校を出席扱いにする」ための次ぐの7つの要件を満たすことが必要です。
ちょっとややこやしいですが、参考までに”文科省の要件”をみてみましょう。
(別記1)
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
引用:”文部科学省の出席扱い要件”
(2)ICT等を活用した学習活動とは,ICT(コンピュータやインターネット,遠隔教育システムなど)や郵送,FAXなどを活用して提供される学習活動であること。
(3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。
(4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)
(5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするなどして,その状況を十分に把握すること。
(6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。
(7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。
だらだらと分かりにくいと思いますので、次に、「すらら」を利用した自宅学習による「不登校でも出席扱いにする方法」を具体的に解説していこうと思います。
すららで不登校の子を出席扱いにするには?

では、先に紹介しました文部科学省の不登校生徒の出席扱い要件をもとに、実際に「すらら」で出席扱いにする方法をみていきましょう!
不登校生徒の出席扱い要件の7項目と、すららを活用して出席扱いとする流れを以下にまとめます。
- 保護者と学校との間に十分なI連携・協力関係があること
- ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること
- 訪問等による対面の指導が適切に行われること
- 学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
- 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
- 学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
- 学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること
※引用:すらら
➀保護者と学校との間に十分なI連携・協力関係があること
不登校のお子さんをすらら学習で出席扱いとしていきたい場合、まずは保護者の方から担任の先生に相談するところから始めます。
文部科学省が取り決めているルールではありますが、まだまだ多くの学校では、すららのようなIT教材を使って「出席扱い」にできることを知らない場合があります。
学校の協力なしには、出席扱いとしていくことは難しいため、すららHPの情報(資料請求でもらえるパンフレット等)を持っていき、文部科学省が制定しているルールを含めて相談を持ちかけましょう!
▼すららの資料請求で「出席扱い」についての情報を収集する!
②ITや郵送、FAXなどの通信方法を活用した学習活動であること
すららは、インターネット環境がありパソコンやタブレットがあれば、どこでも勉強が可能です。
そのため、不登校で家から出られないお子さんでも、しっかり学習することができます。
現在よりも前の学習範囲をさかのぼって勉強することができ、不登校で授業を受けていない場合でも、遅れを取り戻せます。
➂訪問等による対面の指導が適切に行われること
最終的には「学校への復帰」が目的です。
そのため、次のような対面指導する方が必要になります。
- 担任の先生
- スクールカウンセラー
- 保健室
- 適応指導教室
学校によって対応が異なるため、まずは担任の先生に相談しましょう。
④学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
不登校のお子さんが自宅で学習しながら「出席扱い」にするためには、使用する教材は文部科学省の指導要領に対応した「計画的な学習プログラム」であることは必須です。
その点、すららは学習指導要領に対応し、「ラーニングデザイナー」という機能で「学校の理解の程度を踏まえた」学習が可能となっています。
⑤校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること
すららで勉強すると、その日の学習履歴が保存され、「学習管理画面」機能で確認できます。
保護者、担任の先生、校長先生が同じ情報をいつでも共有することが可能です。
⑥学校外の公的機関や民間施設等で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること
すららは、「家に引きこもりがちで人と会いたがらない」、「人間関係がストレスになってしまう」お子さんにおすすめの教材とされます。
お子さんと相談し、自宅で学習を進めるかどうかを決めていきましょう。
⑦学習活動の評価は、計画や内容を学校の教育課程に照らし判断すること
学習評価は、
- 知識・理解
- 技能
- 思考・判断・表現
- 関心・意欲・態度
の4つの観点で判断されます。
不登校で「出席扱い」されただけではすべてを満たすことができないため、学校側とよく協議することが必要です。
たとえば、中学生の高校受験に向けた内申点対策では、評定不能だと「1」がつき、「2」「3」を取るためには、保健室や別室でもよいので、定期テストは受けに行かなければならないでしょう。
成績で「4」「5」を狙いたいなら、学校への復帰が必要となります。
▼すららの資料請求で「出席扱い」についての情報を収集する!
すららで不登校の生徒を出席扱いにするデメリット!

すららで、不登校のお子さんが「出席扱い」になることはありがたい仕組みですが、デメリットとなる点もあるため、以下にまとめます。
- 保護者のサポートが必要
⇒学校とのやり取り、子供の学習状況の確認など、サポート体制が必要。 - 学校との連携が必要
⇒まだまだ、新しい仕組みのため、学校(まずは担任の先生)との協議が必要。保護者の負担もある。 - 出席している生徒に対して、成績は低めとなる
⇒良い成績を取るためには、学校復帰により評価観点を満たす必要がある。
不登校で出席扱いとしていくためには、保護者と学校の連携が、とても重要になってきます。
まずは「すらら」の資料請求で、詳しいパンフレット等を持っておくと、担任の先生との相談がしやすいでしょう。
▼すららの詳細&資料請求はこちら!
【すららのメリット!】不登校のお子さんにおすすめ教材です!
すららのオンライン学習で、不登校のお子さんの「出席扱い」が可能となりますが、そもそもどういう教材なのかが分からない方も多いかと思います。
すららの特長を以下にまとめます。
すららの特長をざっくり紹介!
まずは、すららの学習内容・コース・料金などといった特長をざっくりまとめます。
~すららの概要~
- 学習スタイル
自宅のパソコンやタブレットを用いたオンライン学習 - 学習内容
- 無学年方式
⇒学年をまたいで学習可能。「さかのぼり学習」「先取り学習」ができる。 - すららコーチが保護者サポート
- ゲーム感覚で楽しく勉強できる仕組み
- AI搭載型ドリル
⇒理解度にあった問題を出題 - 学力を測定する診断テスト
⇒日々の理解度チェック、定期テスト対策にも!
- 無学年方式
- 入会金(新規入会時のみ)
- 小中・中高5教科コース
7,700円(税込) - 小中・中高3教科コース、小学4教科コース
11,000円(税込)
≫【お得!】すららのキャンペーンコード・クーポンを徹底解説!入会金無料もあり!?
- 小中・中高5教科コース
- 3教科(国・数・英)コース
- 毎月支払いコース
- 小中コース:8,800円(税込)
⇒小学1年生~中学3年生までの3教科の範囲が学び放題
※英語は中学範囲から - 中高コース:8,800円(税込)
⇒中学1年生~高校3年生までの3教科の範囲が学び放題
- 小中コース:8,800円(税込)
- 4か月継続コース
- 【4ヶ月】小中コース:8,228円(税込)
⇒小学1年生~中学3年生までの3教科の範囲が学び放題になる4ヶ月継続コース。(英語は中学範囲から) - 【4ヶ月】中高コース:8,228円(税込)
⇒中学1年生~高校3年生までの3教科の範囲が学び放題になる4ヶ月継続コース。
- 【4ヶ月】小中コース:8,228円(税込)
- 毎月支払いコース
- 4教科(国・数・理・社)コース
- 毎月支払いコース
- 小学コース:8,800円(税込)
⇒小学1年生~小学6年生までの4教科の範囲が学び放題
※理科・社会は小3~小6の範囲
- 小学コース:8,800円(税込)
- 4か月継続コース
- 【4ヶ月】小学コース:8,228円(税込)
⇒小学1年生~小学6年生までの4教科の範囲が学び放題になる4ヶ月継続コース
※理科・社会は小3~小6の範囲
- 【4ヶ月】小学コース:8,228円(税込)
- 毎月支払いコース
- 5教科(国・数・理・社・英)コース
- 毎月支払いコース
- 小中コース:10,978円(税込)
⇒小学1年生~中学3年生までの5教科の範囲が学び放題
※英語は中学範囲から、理科・社会は小3~中3範囲 - 中高コース:10,978円(税込)
⇒中学1年生~高校3年生までの5教科の範囲が学び放題
※理科・社会は中1~中3範囲
- 小中コース:10,978円(税込)
- 4か月継続コース
- 【4ヶ月】小中コース:10,428円(税込)
⇒小学1年生~中学3年生までの5教科の範囲が学び放題になる4ヶ月継続コース
※英語は中学範囲から、理科・社会は小3~中3範囲 - 【4ヶ月】中高コース:10,428円(税込)
⇒中学1年生~高校3年生までの5教科の範囲が学び放題になる4ヶ月継続コース
※理科・社会は中1~中3範囲
- 【4ヶ月】小中コース:10,428円(税込)
- 毎月支払いコース
- おすすめのタイプ(※タップで詳細記事へ)
▼すららの評判についてはこちら!
すららのメリットはこれ!

繰り返しになる点もありますが、不登校のお子さんを含め、小学生・中学生が「すらら」を受講するメリットは次のとおり!
- 無学年式
⇒すべての単元がいつでも利用できる - お子さんのペースで学習できる
- 集中力が続く仕組み
- すららコーチのサポートがある
- 不登校でも出席扱いの要件を満たすIT教材(条件あり)
不登校のお子さんは、勉強法に不安をお持ちの方も多いかと思います。
すららは、「授業の遅れを取り戻したい」「出席扱いにしたい」という小・中学生に最適な教材となるでしょう!
【小学生・中学生・高校生】不登校生徒の現状は?

現在、小学生・中学生・高校生で不登校の生徒は少なからずおり、先に述べたとおり、文科省が出席扱いの要件を制定するなどの動きも出ています。
不登校でお悩みの親御さん・お子さんにとって、ありがたい制度ですね。
その中で、すららのように「出席扱い」にできる教材が作られ、現在、少しずつこういった制度が実現できる流れができてきています。
不登校でお悩みの方の現状として、文科省が「不登校生徒」の現状を調査していますので、チェックしておきましょう。
不登校の生徒の現状
小学校、中学校・高校において、不登校の生徒の人数は、文部科学省のデータとしても公表されています。
(※文部科学省HP参照。2020年度不登校生徒数。)
| 不登校の人数 | 全生徒数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 63,350 | 6,333,716 | 1.0% |
| 中学校 | 132,777 | 3,244,958 | 4.1% |
| 高校 | 43,051 | 3,098,203 | 1.4% |
不登校生徒の割合としては、数%と少なく見えるかもしれませんが、小学生・中学生・高校生の中で、何かしらの事情で不登校になるお子さんは、少なからずいることになります。
とくに中学校では4%という割合のお子さんが不登校となっており、約25人に1人と多くなっています。
不登校になるきっかけ
文部科学省の調査で、小学生・中学生のお子さんが不登校になるきっかけはさまざまとされます。
(※下表、複数回答ありのアンケート結果。令和2年12月、小6・中2調査)
| 先生のこと | 身体の不調 | 生活リズムの乱れ | 友達のこと | |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 30% | 27% | 26% | 25% |
| 中学校 | 28% | 33% | 26% | 26% |
上記のように、不登校になる理由が多岐にわたってあるようです。
小学生・中学生という発達段階である時期で、環境の変化や、友人・先生などの環境要因によって、学校へ行けなくなることがあります。
不登校でお悩みになる方にとって、すららによる不登校の出席扱いが可能というのはありがたい仕組みです。
「出席扱い」の制度について興味をお持ちの方は、まずは「すらら」の資料請求を利用して、出席扱いの情報収集をしてみるとよいでしょう。
▼すららの詳細&資料請求はこちら!
~すららの受講をお迷いの方~
すららへの入会をお迷いなら、次の手順がおすすめ!
- まずは資料請求!(無料)
⇒すららの全体像・特長を知る! - 無料体験
⇒実際に手に取って使ってみる! - 入会(受講開始)
⇒すららで勉強習慣をつける!
すららなどの通信教育は、資料請求でもらえるパンフレットが上手にできています。
お子さんと一緒にパンフレットを見ることで、「すららの全体像(特長)が分かる」のと同時に、「お子さんのやる気」が出ることもあるでしょう!

僕の中学時代も、進研ゼミのパンフレットを見て、「これなら楽しくできそう」と感じました。
勉強へのやる気も出て、成績アップのきっかけになったと思います。
ちょっとしたきっかけで、小学生・中学生・高校生のお子さんは「やる気」になったりします。
すららの資料請求を利用してみる価値は大きいでしょう。
▼すららの入会はこちら!
(※受講をお迷いなら資料請求がオススメ!)
まとめ
不登校のお子さんでも、すららのオンライン学習教材なら、出席扱いにすることもできます。
自宅での学習で出席扱いにするためには、文科省で定められた要件を満たすことが必要です。
学校の協力を得ながら、「すらら」学習教材を利用して、不登校のお子さんを出席扱いにしてもらいましょう。
出席扱いにするために保護者の方がまずすべきことは、学区の担任の先生に相談するところからです。
不登校生徒の出席扱いは、文科省が制定した制度とは言え、まだまだ学校レベルでは理解が進んでないこともあります。
すららは無料資料請求ができますので、パンフレットを取り寄せて、まずは「不登校の出席扱い」を学校に相談してみましょう!
▼すららの資料請求で「出席扱い」についての情報を収集する!
▼不登校の中学生向け通信教育を紹介!