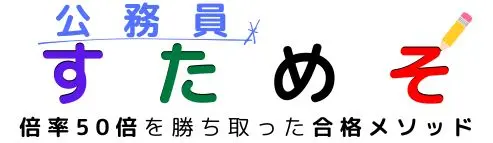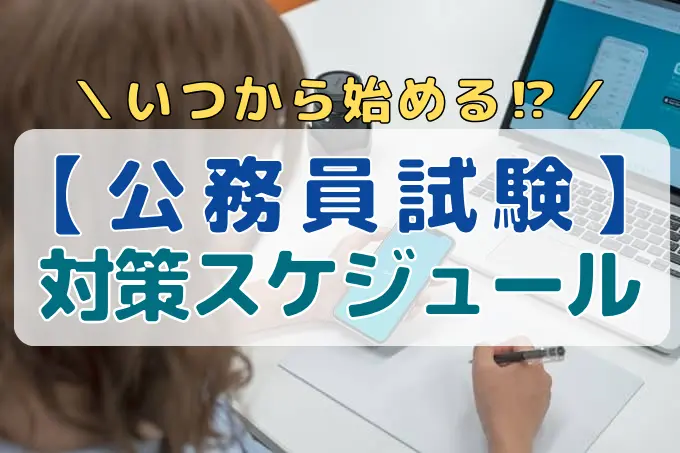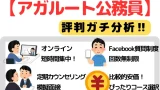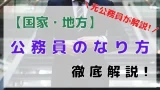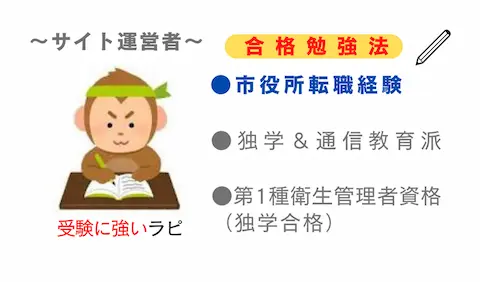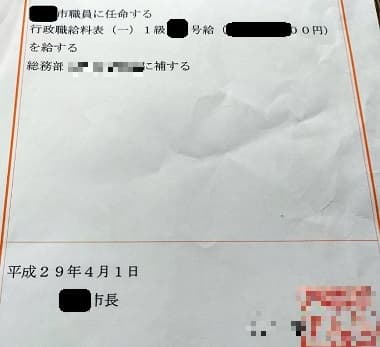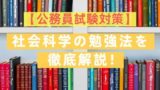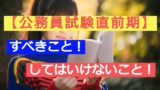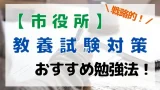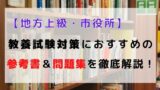公務員を目指そうか迷っているのですが、公務員試験対策はいつから始めたらいいのでしょうか?
そんな疑問にお答えします!
公務員を目指す方にとって、試験対策をいつから始めるべきかは気になるところですよね。
膨大な範囲の学習となる公務員試験対策では、できる限り早く取り掛かるのが望ましいですが、どういうスケジュールで取り組んでいくかは重要です。

目指す公務員にもよりますが、試験対策にざっくりと1年はほしいところです!
本記事は、公務員試験対策を始めるべき時期&勉強スケジュールを徹底解説するので、ぜひ参考にしてみてください!
公務員試験対策はいつから始めるといい?
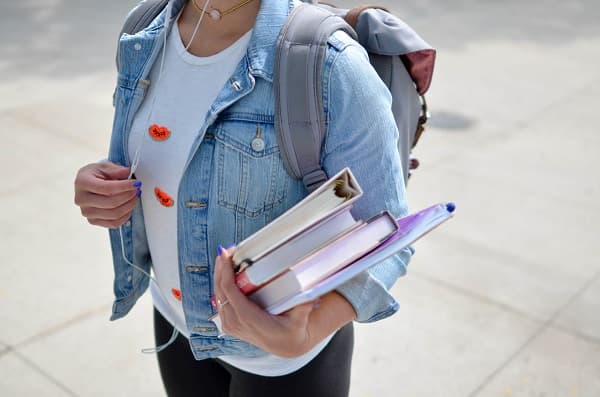
「公務員試験対策はいつから始めるべき?」という問いに対して、なるべく早くスタートすることをオススメします。
基本的には、一次試験(筆記)の1年前からだと、しっかり勉強時間が確保できるでしょう。
公務員試験の試験日程は、以下のとおり!
(※一部の公務員試験スケジュール)
- 6月後半➀:国家一般職
- 6月後半➁:地方上級(県・政令市)、市役所A日程
※地方上級と市役所A日程は同日 - 7月:市役所B日程
- 9月:市役所C日程
- 10月以降:一部の市役所

あなたが受験したい公務員試験の日程は、だいたい毎年同じ時期になるはずなので、例年の試験時期を調べておきましょう。
ちなみに地方上級(都道府県)と、市役所A日程は同日になるため、残念ながら併願はできません。日程がかぶらなければ併願はありです。
それで、国家一般職レベルの試験を突破する実力をつけるのに、1000時間~1500時間は必要と言われます。
そのため、1年かけても単純に1日3時間以上は勉強しないといけません。
新卒の方なら、大学3年生から取り組み始めることになりますが、大学の授業やテスト、実習なんかもあったりするので、簡単なものではないですね。
早めに取り組み始めることをおすすめします!
公務員試験対策に時間がかかる理由とは?

公務員試験の内容は、一般的に次のとおりとなります。
- 1次試験
- 教養試験
- 専門試験
- 2次試験
- 論文試験
- グループワークor面接試験(集団・個別)
- 最終試験
- 個別試験
この中で、特に試験対策に時間を要するのが、「教養試験・専門試験」、次が「論文試験」となるでしょう。
とくに、教養試験と専門試験は、膨大な範囲を勉強することになるので、”完璧主義”で勉強していくと、1年でもきついかもしれません。
では、各試験の具体的内容をまとめます。
(※教養・専門の科目は、公務員試験で主として取り上げられるものを取り上げています。)
~教養試験~
- 文章理解(現代文・古文・英語)
- 数的処理(数的理解・判断推理・資料解釈)
- 社会科学(法律・政治・経済・社会・時事)
※「法律・政治・経済・社会」は専門と重複のため、専門対策をするなら、「時事」対策のみ行う! - 自然科学(数学・物理・化学・生物・地学)
- 人文科学(日本史・世界史・地理・思想・文芸)
~専門試験~
- 法律系(憲法・民法・行政法・労働法・刑法)
- 行政系(政治学・行政学・社会学)
- 経済系(ミクロ・マクロ・財政学・経営学・会計学)
~論文試験~
- テーマに沿った記述試験
~面接試験~
- 個別面接
- 集団面接
- グループワーク など
教養試験と専門試験は、高校レベルの国語・数学・理科・社会・英語で習うような試験になりますので、対策にはかなりの時間を要します。
「うわ~、公務員試験って大変なんだな・・・」と思うかもしれませんが、みんな同じ条件で試験を受けます。
その中で、しっかり合格を勝ち取る人は、「効率的」に学習できた受験生です。
「出題傾向」・「得意・苦手分野」をみて、重点科目&捨て科目を区別しながら、本番でより多くの得点を取るため対策をします。
そして、しっかり本番で戦えるだけの力をつけるために、試験までの学習スケジュールを立てて、計画的に取り組んでいきます。
あとは、コツコツがんばるだけ!
やみくもに公務員試験対策を始めるのではなく、スケジュールも含めてしっかり作戦を立てていきましょう!
公務員試験対策の具体的なスケジュールは?

では具体的にどのように公務員試験対策を行っていくか、スケジュールの一例を紹介していきます。
以下に、科目ごとにスケジュール例を組みましたが、教養の「社会科学(政治・経済・法律・社会)」については、専門で学習する科目と内容がかぶりますので不要としています。
(※専門対策する受験生は、時事のみ学習する!)
では、国家一般職や地方上級の日程(6月下旬の1次試験)に合わせて、1年前からのスケジュールを組んでみましょう!
(各科目の具体的な取り組みとしては、問題集を1冊決めて、3周程度繰り返すようにしましょう。)
公務員試験対策スケジュール:6~12月(大学3年生)
~教養試験対策スケジュール~
| 科目 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文章理解 (現代文・古文・英語) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 数的処理 (数的・判断・資料) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自然科学 (数学) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 自然科学 (物理・化学) | 〇 | 〇 | |||||
| 自然科学 (生物・地学) | 〇 | 〇 | |||||
| 人文科学 (日・世・地・思・文) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 社会科学 (時事のみ) | |||||||
| 論文 |
※専門試験を受験しない方は、社会科学(法律・政治・経済・社会)の対策も必要になるので、下表の重複分野の対策時期に組み込んでいきましょう。
~専門試験対策スケジュール~
| 科目 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律系 (憲法) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 法律系 (民法) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法律系 (行政法) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 法律系 (労働法) | |||||||
| 法律系 (刑法) | 〇 | 〇 | |||||
| 行政系 (政治学) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 行政系 (行政学) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 行政系 (社会学) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 経済系 (ミクロ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 経済系 (マクロ) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 経済系 (財政・経営・会計) | 〇 |
~Point~
- 数的処理の中でも、数的理解・判断推理はとくに時間がかかるので、まず優先的に始める。
軌道に乗ったら、資料解釈や、文章理解(国語・英語中心)も始めていく。 - 専門試験は、民法から攻める。
- 取りかかり始めの時期は、「対策に時間がかかるもの」、「重要科目であるもの」から始めていく。
- 早めに取り組んでいる科目の参考書は、12月中に2周は終わらせる。
公務員試験対策スケジュール:1~3月(大学3年生)
~教養試験対策スケジュール~
| 科目 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| 文章理解 (現代文・古文・英語) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 数的処理 (数的・判断・資料) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自然科学 (数学) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自然科学 (物理・化学) | 〇 | 〇 | |
| 自然科学 (生物・地学) | 〇 | ||
| 人文科学 (日・世・地・思・文) | 〇 | 〇 | |
| 社会科学 (時事のみ) | 〇 | ||
| 論文 |
※専門試験を受験しない方は、社会科学(法律・政治・経済・社会)の対策も必要になるので、下表の重複分野の対策時期に組み込んでいきましょう。
~専門試験対策スケジュール~
| 科目 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|
| 法律系 (憲法) | 〇 | ||
| 法律系 (民法) | 〇 | 〇 | |
| 法律系 (行政法) | 〇 | 〇 | |
| 法律系 (労働法) | 〇 | 〇 | |
| 法律系 (刑法) | 〇 | ||
| 行政系 (政治学) | 〇 | ||
| 行政系 (行政学) | 〇 | ||
| 行政系 (社会学) | 〇 | ||
| 経済系 (ミクロ) | 〇 | ||
| 経済系 (マクロ) | 〇 | 〇 | |
| 経済系 (財政・経営・会計) | 〇 | 〇 | 〇 |
~Point~
- 参考書を2周目、3周目とどんどんこなしていく。
- 教養試験対策では、3月頃から時事に取り組み始めて本番までに一気に仕上げる。
- 専門試験では、労働法や財政学にも手をつけ始め、一気に仕上げていく。
公務員試験対策スケジュール:4~6月(大学4年生)
~教養試験対策スケジュール~
| 科目 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 文章理解 (現代文・古文・英語) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 数的処理 (数的・判断・資料) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自然科学 (数学) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自然科学 (物理・化学) | 〇 | 〇 | |
| 自然科学 (生物・地学) | 〇 | 〇 | |
| 人文科学 (日・世・地・思・文) | 〇 | 〇 | |
| 社会科学 (時事のみ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 論文 | 〇 | 〇 | 〇 |
~専門試験対策スケジュール~
| 科目 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 法律系 (憲法) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法律系 (民法) | 〇 | 〇 | |
| 法律系 (行政法) | 〇 | 〇 | |
| 法律系 (労働法) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 法律系 (刑法) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 行政系 (政治学) | 〇 | 〇 | |
| 行政系 (行政学) | 〇 | 〇 | |
| 行政系 (社会学) | 〇 | 〇 | |
| 経済系 (ミクロ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 経済系 (マクロ) | 〇 | 〇 | |
| 経済系 (財政・経営・会計) | 〇 | 〇 | 〇 |
~Point~
- 公務員試験直前期になるので、徹底的に総復習、実戦問題演習を行う。
- 時事を仕上げる。
- 論文の対策を始める。
公務員試験直前期の勉強法については、別記事で詳しくまとめていますので合わせてお読みいただくと良いです。
スケジュールの全体総括
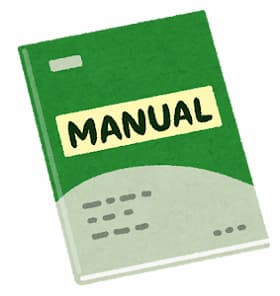
各科目の対策スケジュールをまとめましたが、あなたが目指す公務員によっては、出題率が低いものなど不必要な科目もありますし、捨て科目も作っていくべきです。
一度、出題傾向などを分析して、あなたなりのスケジュールを組んでみましょう!
また、必ずといっていいほど、予定より「遅れるもの」や意外と「早く進むもの」も出てきます。
そのときには、臨機応変にスケジュールを組みかえたりすればOKです。
ここで紹介したスケジュールは参考ではありますが、各科目の開始時期については参考にしていただくと、スケジュールが組みやすいと思います!
公務員試験対策を始めるのが遅れてしまったけど大丈夫?

とくに大学生の方は、就活か公務員試験受験かとても迷うと思います。
「公務員になろう!」と決心するのが遅くなってしまうこともアルアルですが、試験まで1年を切ってしまったときにどうすべきか・・・
この疑問に対して、結論は諦めなくてOKです。
この場合の対策は次のとおりです。
- 一日の勉強時間を増やす!
⇒時間的に可能であれば、短期集中は効率良い! - 捨て科目を作る!
⇒効率よく本番での得点を伸ばす。足切りラインを突破することを目指す!
とくに、捨て科目(分野)を作るという考え方は、一次試験を突破するためには全員に必要な要素です。

捨て科目を作るということは、決して楽をするということではありません!
捨て科目で空いた時間を「より得点できる科目に力を注ぎこむ」ことを目的とします。
最新の試験傾向を分析しながら、力を入れるところと入れないところを決めましょう。
スタートが遅れれば、遅れただけ不利にはなりますが、巻き返す方法はあるので諦めずにがんばりましょう!
公務員試験対策におすすめの学習法!
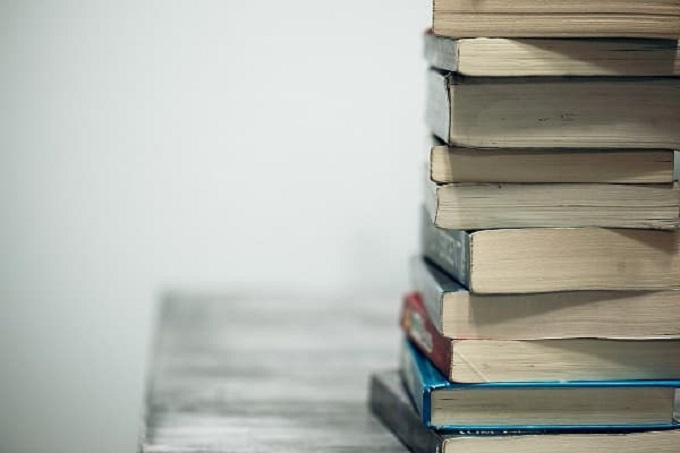
公務員試験を目指すための学習法をまとめます!
公務員予備校の利用がベター
公務員試験対策では、ダンゼン予備校の利用が有利です。
その理由は次の3つ!
- 公務員試験対策に必要な学習が分かる
- 試験対策用の教材が手に入る
- 面接などの二次試験対策ができる
⇒公務員試験に向けて、効率的&効果的な対策が可能!

僕は独学でしたが、試験対策を始める時に「何を勉強すればいいのか」という点が一番苦労しました!
試験対策のスケジュールを組んでいる間も、予備校生は学習を進めているので焦っちゃいますよね・・・
今では、オンラインで自宅で取り組めるアガルートなどの予備校もあるので、無料体験を利用するなどして受講を検討してみるのもありでしょう。
独学におすすめの参考書!
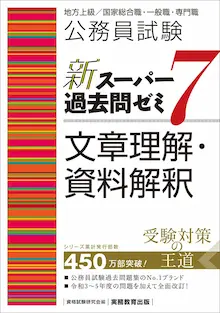
公務員試験対策は独学で取り組みたい方は、参考書選びが大切!
基本的に、過去問などを解いて進めていく「問題集色」の強い教材がオススメです。
王道の「スー過去(新スーパー過去問ゼミ)」や、数的処理なら「畑中敦子シリーズ(ザ・ベストなど)」が人気かなと。
公務員試験向けの参考書については、下記事でも詳しくまとめているので、あわせて参考にしてみてください!
まとめ
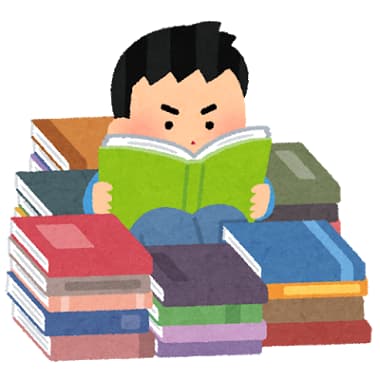
「公務員試験対策っていつから始めるの?」という疑問に対して、結論今からスタートすべきです。
なるべく早く始めるのが有利ですが、できれば試験1年前には始めたいところ。
国家一般職や地方上級、市役所レベルなら、試験対策にトータル1000時間以上あるとよいでしょう!
もし、就活と迷っていてスタートが遅くなってしまった方は、捨て科目を作るなどしてより効率的に学習を進めるようにしましょう。
▼確実に合格を勝ち取るなら予備校利用がベスト!