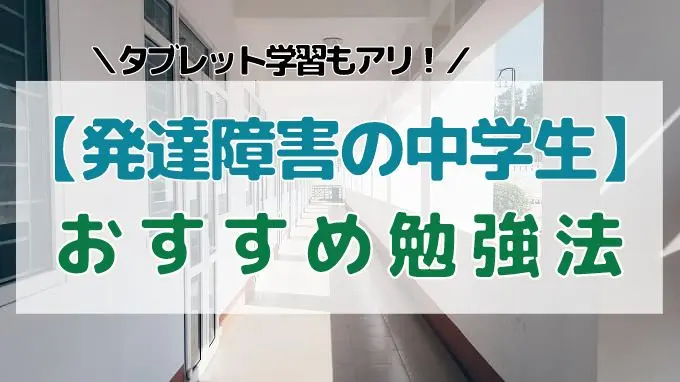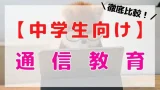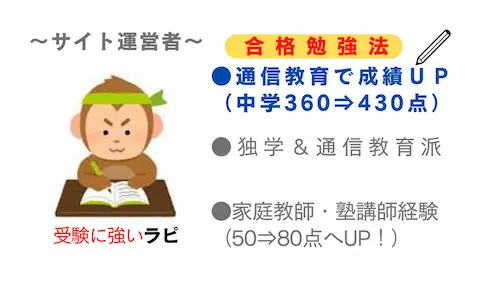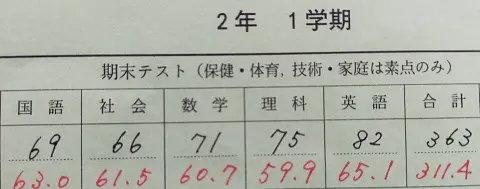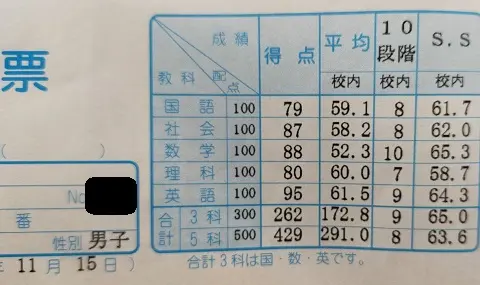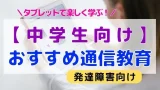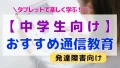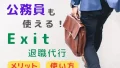~本記事のテーマ~
- 発達障害の中学生で、勉強しないときの対処法は?
- 発達障害やグレーゾーンの中学生におすすめの勉強法は?

どういう勉強法がいいのかしら?
そんな疑問にお答えします!
発達障害やグレーゾーンの中学生にとって、勉強はハードルの高いもの。
ただ「勉強しなさい」では、学力の定着や成績アップは難しいため、勉強法の工夫が必要です。
本記事では、発達障害の中学生向け勉強法を紹介します!
発達障害が勉強を苦手とする理由を含め、オススメ教材等を徹底解説するので、ぜひ参考にしてみてください!
【中学生にも多い!?】発達障害とは?

まずは、発達障害についてざっくりチェックしていきましょう。
発達障害の定義
発達障害とは、発達障害者支援法により以下のように定められます。
(※参照:文部科学省HP「発達障害について」)
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
発達障害の小中学生は、10%弱在籍していると推計されます。
(※参照:NHK)
決して少なくない人数とは言えないでしょう!
発達障害の種類
発達障害の中学生は、症状別に次の3タイプに分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動性)
⇒じっとしていられない、思いつくと行動してしまうといった症状が見られる。 - ASD(自閉スペクトラム症)
⇒自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害など。コミュニケーション面を困難とする。 - SLD(限局性学習障害)
⇒読み・書き・計算を困難とする。
※診断基準を満たさない状態のお子さんは、グレーゾーンと呼ばれる。
発達障害の中学生は、さまざまな症状を持ち、「勉強しない」「勉強への集中力がない」といったことが起きます。
中学校の学力を定着していくためには、勉強法を工夫していく必要はあるでしょう。
発達障害の中学生が勉強しないワケとは?
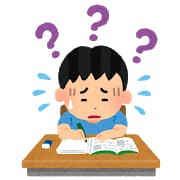
発達障害の中学生は、「勉強しない」「勉強できない」といったお悩みのお子さんは多いです。
まずは、発達障害の特性&勉強しない理由をチェックしていきましょう!

発達障害のお子さんに対して、やみくもに「勉強しなさい」では成績は伸びません。
「勉強しない理由」を知っておくと良いでしょう。
| 発達障害の特徴 | |
|---|---|
| ADHD (注意欠如・多動性) | ・集中できない ・忘れ物が多い ・計画的に勉強ができない |
| ASD (自閉スペクトラム症) | ・中学の友達とコミュニケーションが取れない ・興味のない科目に、やる気が出ない |
| SLD (限局性学習障害) | ・勉強しても理解できない教科がある ・受験勉強で難易度の高い学習で意欲を無くしがち |
発達障害と言っても、さまざまなの症状を持つお子さんがいます。
高校受験も控える中学校の勉強は、難易度の高い学習も必要に。
それぞれの特性に合わせた、勉強法を構築していくと良いでしょう。

いろんなタイプの発達障害があり、お子さん一人ひとりにあった対応をしていくことが大切。
困ったときは、中学校や支援センター、医療機関などの専門家に相談するのもありです。
発達障害の中学生におすすめの勉強法!
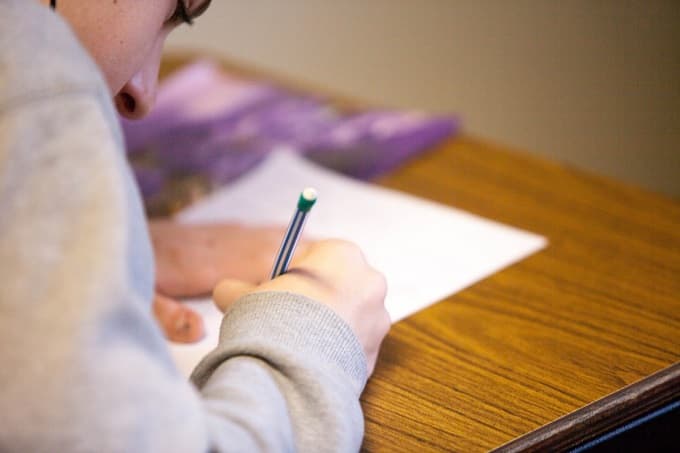
発達障害の中学生向け勉強法をチェックしていきましょう!
勉強のサポートは必要!

発達障害のお子さんにとって、勉強はハードルの高いもの。
日々の学習を進めていく上で、保護者等のサポートは必要でしょう。
- 子供の気持ちに寄り添う
- 無理に勉強させない
- 勉強法の工夫(紙⇒タブレット、対話形式、動画・音声学習など)
「ほったらかしにしない」「無理に押し付けすぎない」といったように、上手にサポートしていくことが大切です。
まずは、「勉強しやすい環境づくり」に徹し、ゆっくりと学習習慣を付けていけるようにしましょう。
褒めることは効果大!
発達障害の中学生は、勉強へのニガテ意識を持つことも多いです。
「褒める」ことで、勉強への「自信」や「やる気」を持つようになります!
タブレット等のデジタル学習がオススメ!

発達障害のお子さんの勉強法として「塾」を検討する方もいるかもしれませんが、人とのコミュニケーションが苦手なら、自宅で学習できる通信教育がオススメ!
中でも、タブレットやパソコンを用いた「デジタル学習」は、勉強へのハードルも低いでしょう!
~タブレット学習(デジタル)のメリット~
- タブレットなら勉強に取っ掛かりやすい
- タブレットならアニメーションや音声付で楽しく学習できる
- 場所を選ばず学習できる
発達障害の中学生向けのデジタル学習なら、すららは有名どころ。
無学年式で着実にレベルアップしていく仕組みのため、「勉強がニガテ」なお子さんにもオススメです。
まずは資料請求で、詳細をチェックしてみると良いでしょう!

タブレット等を用いたデジタル学習(通信教育)は、塾に比べて安価に受講できます!
受講へのハードルも低く、試しに利用してみる価値はあるでしょう。
まとめ
発達障害の中学生は、勉強法の工夫が重要です。
保護者のサポートや、タブレット・パソコンを使ったデジタル学習を利用するなど、「勉強しやすい環境」を作ってあげることが大切。
すららなどの通信教育は、「発達障害の中学生」にも学習習慣が付けやすい仕組みとなっているため、まずは資料請求でチェックして見ると良いでしょう!
\発達障害にもオススメのオンライン学習!/