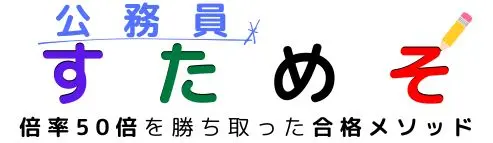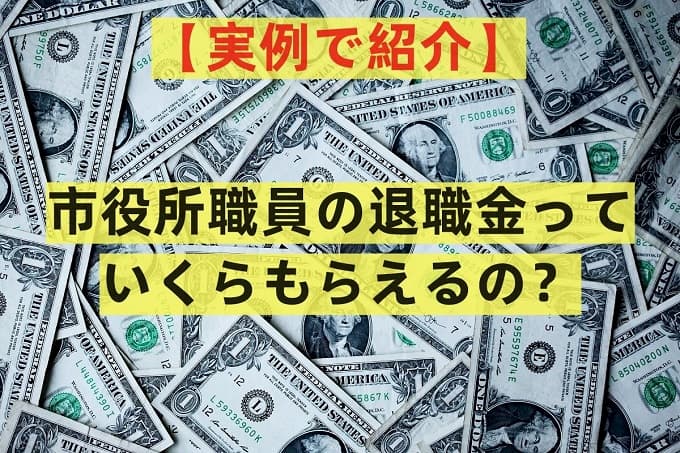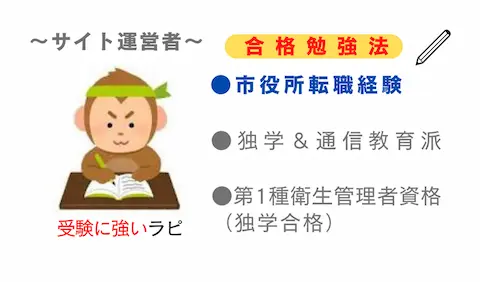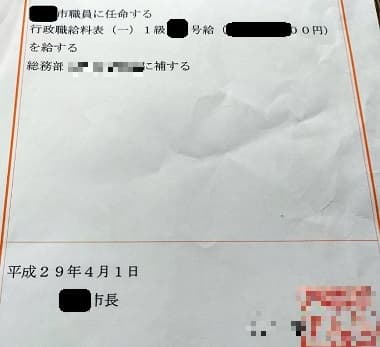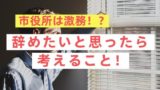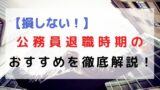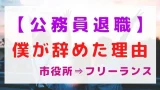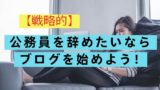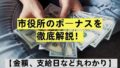~本記事のテーマ~
- 市役所職員の退職金の決め方を紹介!

市役所職員の退職金は、いくらもらえるんですか?
市役所の退職金については、条例であったり、HPで公開されていますので、調べ方が分かれば、あなたが目指す市役所もすぐに分かりますよ。
この記事では、市役所の退職金について具体的に解説していくとともに、あなたが知りたい情報に合わせて調べられるように、調べた根拠なども載せて紹介していきます。
~この記事がおすすめな人~
- 市役所職員として勤めていて、定年退職だとどれくらいの退職金がもらえるか気になっている!
- 市役所を早期退職すると、退職金がいくらもらえるのか知りたい!
- 市役所を目指していて、退職金ってどれくらいもらえるのか知りたい!
▼公務員を辞めようかお悩みの方はこちらがおすすめ!
市役所職員の退職金の決め方!
市役所職員がもらう退職金のことを、退職手当と言います。
退職手当は、
基本額+調整額
※基本額=退職日給料月額×退職理由別・勤続年数別支給率
となります。
地方自治法という法律で、職員の給料や手当に関しては各自治体の条例で定めることになっており、市役所の退職手当も、自治体ごとで条例を作ってありますので、ちゃんと働いていれば必ず退職金は必ずもらえます。
それは、定年退職であっても、自己都合退職であってもです。
市役所職員って退職金はいくらもらえる?

では、具体的に市役所職員が退職金をいくらもらえるかについて、様々な市を例に見ていきましょう。
※各市のHP(リンクあり)より平成30年度の支給実績。表記金額は切り捨て後の数字。
平均支給額では、定年退職でだいたい2000万円くらいもらっていますね。
※岡山市はやや少ないですが、自己都合退職者を含めた平均になっています。
勤続年数により、〇か月分という係数が大きくなっていきますが、現在(2020年3月時点)の最大限度額は47.709か月分のようです。
そのため、勤続35年以上勤めても47.709か月分になります。
大学卒で勤めれば、最大の係数になるでしょうし、けっこうもらえることになりそうですね。
一方、自己都合退職の場合はというと、定年退職よりも係数は小さくなり、同じ勤続年数でも金額は少なくなります。
参考に、国家公務員の退職金手当支給率早見表をみてみましょう!
(参考:内閣官房HP「国家公務員の退職手当制度の概要」)
| 勤続年数(年) | 定年・勧奨等(か月) | 自己都合(か月) |
|---|---|---|
| 1 | 0.837 | 0.5055 |
| 3 | 2.511 | 1.5066 |
| 10 | 8.37 | 5.022 |
| 15 | 16.216875 | 10.3788 |
| 25 | 28.0395 | 33.27075 |
| 35 | 47.709 | 39.7575 |
| 43 | 47.709 | 47.709 |
国家公務員と市役所では、厳密に言うと退職金の定めは異なる可能性がありますが、たいていは、市役所など地方自治体で制定している条例は、国家公務員の制度から準じて作っている場合が多いため、参考にできるかと思います。

実際に、僕が市役所を3年で辞めたときも、自己都合退職として、だいたい×1.5か月分の支給でした。
これを見ると、定年退職の場合と自己都合退職の場合で、給料月額の何か月分もらえるんだろうなというのが分かります。
各自治体でも、こういった係数表が見られればチェックしてみるとよいですし、すでに市役所職員の方は、労働組合の冊子なんかでも載っているかもしれません。
退職金支給率早見表があれば、あとは給料月額を見ればOK!どれくらいもらえるかが分かりますね。
まとめ
市役所職員の退職金は、条例等で支給要件・金額等が定められています。
ポイントをまとめます。
- 市役所職員の退職金は、条例で定められており、ちゃんと働けばもらえる。
- 退職金の金額は、月給×理由別・勤続年数別支給率+調整額である。
- 退職員の金額は、国家公務員の退職手当支給率早見表を見ると分かりやすい。
本記事が、市役所を目指している人などの参考になればと思います。
~公務員の退職をお考えの方向け記事~
▼公務員を辞める?メリット・デメリットは?
▼公務員を辞めたいと思ったら考えること!
▼公務員で20代の方向け!
▼転職の仕方!
▼退職時期のおすすめ!
▼退職を申し出る時期のおすすめ!
▼僕が公務員を辞めた理由!
▼「ブログで稼ぐ!」に興味がある方向け!